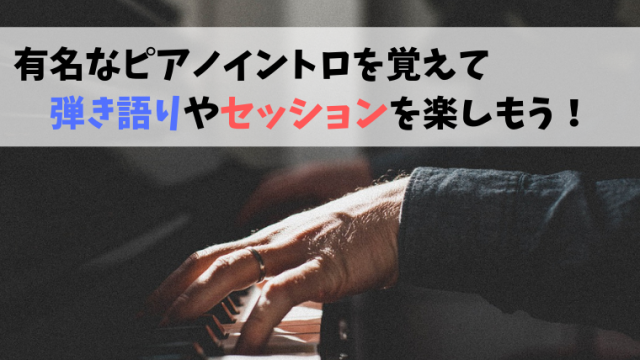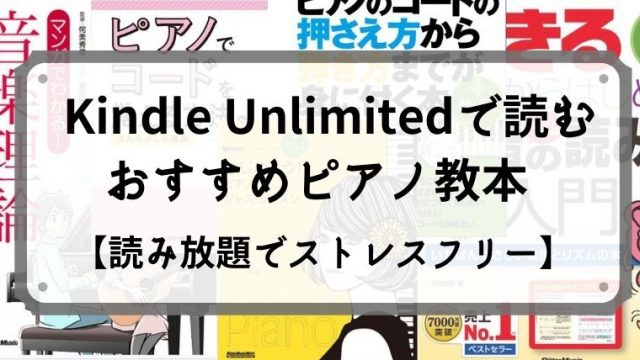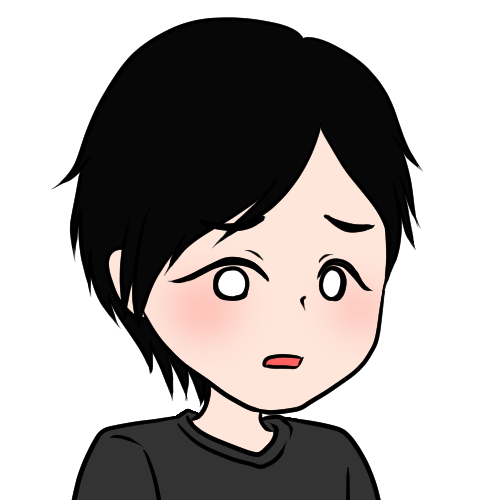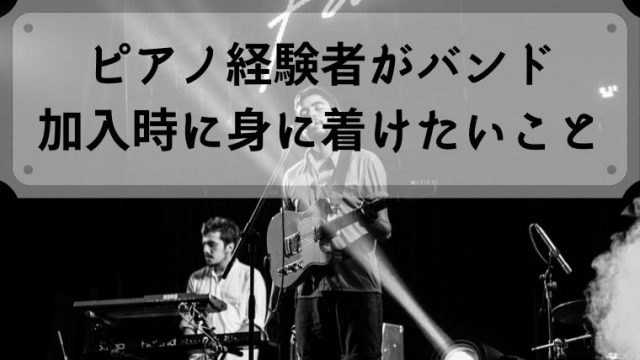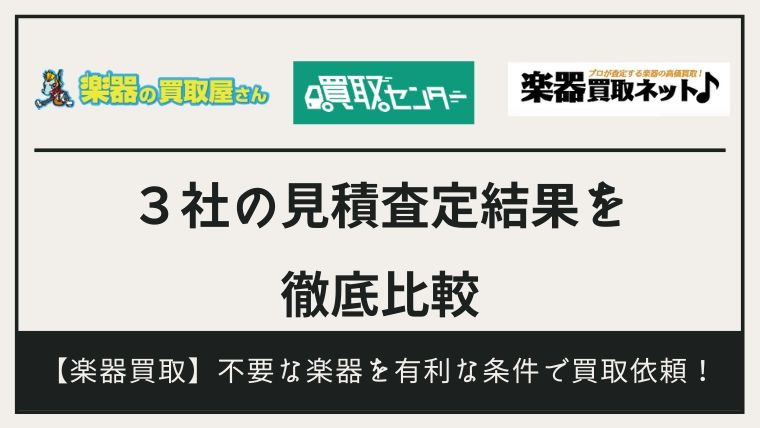こんにちは、カフェランです。
楽器初心者同士に限らずバンドを組んだ際、「さて何の曲やろうか?」という相談は必ずといって行われるものです。
そこで、それぞれ好きな曲や出来そうな曲を提案すると思うのですが、特に初心者バンドは各自の技術レベルがバラバラだったりしますので、こんな声が出始めます。
などなど、すんなりまとまらなかったりします。
今回は、そんな初心者中心のバンドがコピーするのに適している曲として「Stand By Me(スタンド・バイ・ミー)」をおすすめさせていただきます。
以下記事で、どういった部分が適しているのか、そして各パートの弾き方等について詳しく解説しますので、是非参考にしてみてください!
楽曲「スタンド・バイ・ミー」解説
 映画「スタンド・バイ・ミー」
映画「スタンド・バイ・ミー」
まずスタンド・バイ・ミーという曲の基本的な事項です。
映画
実はこの曲は1986年にアメリカで公開された同名(Stand By Me(スタンド・バイ・ミー))の映画の主題歌としても有名です。ただ、映画の方は知らなくても曲は聴いたことある、という人の方が多いかもしれませんね。
映画はあの”ホラー小説家の巨匠”スティーブン・キング原作の「恐怖の四季」という中編作品集に収められている「ゴールデンボーイ」という作品が元なっているもので、少年時代のひと夏の冒険をノスタルジーに描く名作です。
楽曲
元々この曲は、1961年にアメリカの歌手ベン・E・キングの曲としてリリースされました。つまり今から60年近く前に生まれた曲というわけです。
その後、1975年にジョン・レノンがカバー、そして1986年に映画「スタンド・バイ・ミー」の主題歌として採用され、リバイバルヒットした、という経緯があります。
日本でも数多くのCMソングとして採用されてきた他、中学校の英語の授業でも取り入れられるなど、とにかく有名な曲であると言えます。
こちらが曲のオリジナルバージョンです。
出典:
そして有名であるがゆえ、数多くカバーされている曲でもあります。
こちらのサイトでジョン・レノンをはじめとしたカバーソングをうまくまとめられていますので、参考にどうぞ。
NEVERまとめ「スタンドバイミー Stand By Meカバー曲まとめ」
楽曲コピーの考え方
さて「スタンド・バイ・ミー」がコピーする対象の曲としてなぜ適しているかという理由を解説する前に、まずは曲をコピーする際の考え方を整理しておきたいと思います。
初心者同士でバンドを組み、コピー曲を演奏しようとした場合、多くは「完全コピー」(いわゆる”完コピ”)を目指す傾向にあると思います。
これは何故かというと、基本的にはバンドスコアを購入して各パートの演奏を覚えていくやり方をするためで、経験がないゆえに、目の前の教科書に基づいて行うという、ある意味理にかなった方法です。
ただし、バンドスコアをうまく活用する分にはすごく有効ですが、譜面に忠実に従うという意識が固定されてしまうと、融通がきかず、少し難しいフレーズが登場すると「いつまでもその部分で苦戦する」ひいては「曲自体いやになってしまう」などの状況が生まれやすくなります。
コピーはいい意味で”適当”でいいです
実際に、上記でご紹介したオリジナル曲に対するカバーは、実に様々な演奏になっていますよね。(そもそも原曲自体があまりバンドサウンドではないですしね)
”アレンジする”って捉えると少し難しくなるので、「出来ない部分があれば出来る範囲で工夫する」くらいの気持ちで望んだ方が楽しいし、楽です。そして、実はそこから発展してくることも多くあります。
初心者の早い時期からそういった、自分たちなりの演奏というところを意識していくと、幅も広がるし、結果的に上達も早いと思います。
そういったスタンスで取り組む曲として適しているのが、この「スタンド・バイ・ミー」なんです。
もちろん、初心者とか関係なく、バンドの方向性として完コピを目指すバンドも当然あります。そういったバンドは、技術レベルも含め高いレベルを目指すバンドとしてやり甲斐があるものです。
コピーバンドの活動形態等に関する記事も書いています。

つきつめて考えていくと、”再現の音楽”クラシックと、”くずしの美学”ジャズの違いに近いかもしれません

初心者バンドのコピー曲に適している理由
さてここからはが「スタンド・バイ・ミー」がコピーする曲としてなぜ適しているかという理由の解説です。主な項目は次の3点です。
- 曲自体がすごく有名
- 曲構成がシンプルであるため演奏の難易度が低い
- 実は上級者も”セッション”として楽しめる曲
では、1項目ずつ説明します。
①曲自体がすごく有名
コピー曲を選定する上で、”有名で、もともと知っている曲”というのは、それだけでアドバンテージがあります。
なぜなら、誰もが知る曲というのは、コピーする曲として採用しやすいからです。冒頭の曲決め場面のように誰かが「その曲知らない…」となれば曲の説明や音源を聴いてもらうところからのスタートになります。
イメージレベルであっても、メンバー間で曲の共有が出来ていれば話は早いです。
そういった意味では発表から60年近く経つこの曲は、世代を超えて共有され、学校の授業でも題材になるなど若い世代も耳にしている曲です。
また、人前で演奏することを考えても適しています。
演奏を聴く側からすると知らない曲を演奏されるより、少しでも耳にしたことある曲の方が嬉しいものです。そういった意味でも、一つレパートリーにいれておいて損はない曲でしょう。
②曲構成がシンプルであるため演奏の難易度が低い
この曲のイントロ、Aメロ、サビともに次の8小節で構成されています。

なんと、1曲を通じて登場するコードはたった4つです。
基本的には、この8小節のコード進行を繰り返す構成となっているため、とてもシンプルで覚えやすいといえます。
そして、登場するコード自体もトライアドコード(3つの音で構成された和音)のみです。
特に初心者のうちは「スムーズにコードをおさえる」という行為に慣れていない場合がありますので、そういった観点からも演奏の難易度が下がるでしょう。
もし、もっと簡単なコード進行にしたい場合はキーを変えることで対応できます。
例えばキーを一音さげてG(原曲はキーA)にすると次のコード進行になります。

ギターにとっては、バレーコードを使う必要がないので、より演奏が簡単なコード進行といえます。(ギターを始めたての人にとっては、Fなどのバレーコードが苦手という人も多いです)
コード進行はこちらのサイトで確認できます。
③実は上級者も”セッション”として楽しめる曲
実は演奏に熟練した中級、上級者にとっても、このスタンド・バイ・ミーは、セッションのスタンダードナンバーとして定番になっています。
【セッション】
バンドにおける”セッション”とは、その場のノリで曲やテーマ、コード進行等のみを決めて演奏すること
なぜセッションのスタンダードナンバーとして、このスタンド・バイ・ミーが使われているかというと、大きな理由は前項でも説明した、シンプルなコード進行になります。
セッションはその場のノリで行うため、あまり複雑な構成は適しません。
セッションでは”循環コード”といって、ある一定のコード進行を繰り返すことが好まれますが、スタンド・バイ・ミーはまさに、その循環コードなのです。
スタンドバイミーの各コードの機能はこのようになっています。
A :トニック(ルート)
F#m:トニックの代理コード
D :サブドミナント
E :ドミナント
F#mは機能的にAの代理コードであるため、Aとみなすことができます。
そのように捉えるとこの進行というのは、3コードによるブルース進行といえます。
ブルース進行は、3コード(トニック、サブドミナント、ドミナント)による12小節のコード進行のことですが、スタンドバイミーはそのフォーマットに則った曲であるため、非常に自由度が高く、セッション向きの曲といえます。
初心者もいずれ、中級、上級と階段を上っていくでしょう。
初心者の頃は、シンプルな曲構成をシンプルに演奏することで、「音楽を演奏する」という喜びを知り、スキルが向上するごとに、曲の中で色々なことができるようになる。そして更に面白くなる。
そんなバンドの成長を受け止められるような曲でもあります。
各パート別解説
では、ここからは各パートの演奏例について触れていきます。
先ほど述べたようにオリジナルは、バンドアンサンブル感がうすいので、ジョンレノンのカバーバージョンをベースに考えてみます。(バンドスコアを基本的に使わない方法で解説していきます。)
ボーカル

英語詩ですが、中学の授業でも題材になるくらいですので、それほど難しい単語等はでてきません。
音程はサビで最高音がA5(中央のAから1オクターブ上)ですから、人によっては少し高いかもしれません。その場合はGなどにキーを落としてみるのもいいと思います。
音程はボーカリストに合わせるのが基本ですからね。
ギター

コードが4つだけなので、まずはそのコードを確実に抑えられるようにしましょう。
ジョンレノンのカバーバージョンのような雰囲気を出すのであれば、ギターはコードストローク中心でいいと思います。この場合アコースティックギターがいいですが、エレキギターのクリーントーンでも問題ないです。
間奏はギターソロに挑戦しましょう。
基本的には、Aメジャースケールを使ってソロが構成されていますので、まずはAメジャースケールの構成音を把握しておきましょう。
ジョンレノンのカバーバージョンでは、それほど音数も多くないため、スケール構成音に基づき、目立つ音を拾っていけば(耳コピ)、十分弾けると思います。
ジョンレノンのカバーバージョンではスライドギターも登場しているため、そのままのニュアンスはなかなか出せないかもしれませんが、雰囲気出ていればOKです。
キーボード

ギターと同じく4つのコードをおさえられるようにしておきます。
キーボードは色々なアプローチが出来ますが、例えばギターがコードストロークをやっている場合は、キーボードで細かくリズムを刻む必要はないため、各小節の頭にピアノのコードを入れてあげるなどします。
サビでは、一転してオルガンの白玉コードを入れることで、曲の雰囲気を変えることで盛り上がりの演出をしましょう。
とにかく、ギターと音域ややっていることがなるべく被らないよう、相談してみてください。
これがセッションであれば、”ソロ回し”といって、各パートが一定の小節(この曲の場合であれば8小節や16小節)に渡ってアドリブソロを弾きます。
ベース

この曲のベースは何といっても、オリジナルの有名なベースラインですよ!ベース始まりの曲でもあるので、是非オリジナルのラインを取り入れたいところです。
これは、じっくり音を聴いて指板上で確認すればすぐ耳コピできると思います。
あと曲中ほぼ同一ラインですので、安定感がでるよう練習しましょう。
ドラム

ドラムは基本的に8ビートです。
まさにドラムを始めて間もない人の練習曲としても、ちょうどよい難易度だど思います。
フィルインはオリジナルどおりでなくとも、いくつかのパターンを覚えて、サビの前など曲の展開する場面に入れることで、うまく盛り上げることができます。
まとめ
楽器初心者バンドにおける、おすすめコピー曲として「スタンド・バイ・ミー」を紹介させていただきました。
最後に曲の要点だけまとめます。
- 登場するコードは4つだけ
- コード進行は8小節のパターンを繰り返す
- 演奏のポイントはシンプルに。(ギター、キーボードはコードを押さえる、ベースは有名なベースラインを、ドラムは8ビート)
本文でも触れましたが、バンドスコアを元に忠実な再現を求めるのも一つのやり方です。ただ、こういったシンプルな構成、コードの曲を自分たちなりに演奏するのも、非常に面白いし、シンプルだからこそ、創意工夫が生まれ、そこから発展していくものも多いです。
きっと想像するよりも難易度は低いと思いますので、初心者の方にこそ是非試していただきたいです。
Amazonが提供する”Amazon Music Unlimited”は、
6500万曲が聴ける音楽サブスクリプションの中でもトップクラス!
今なら30日無料で聴き放題です。是非この機会に!