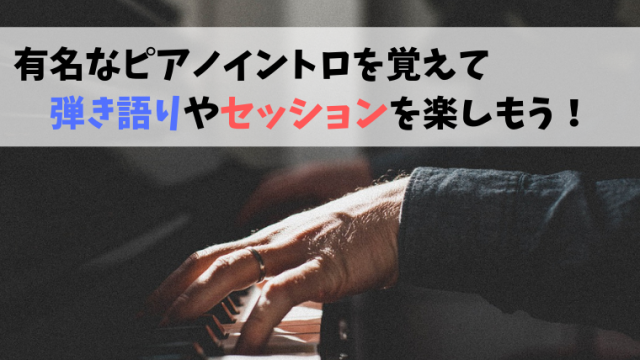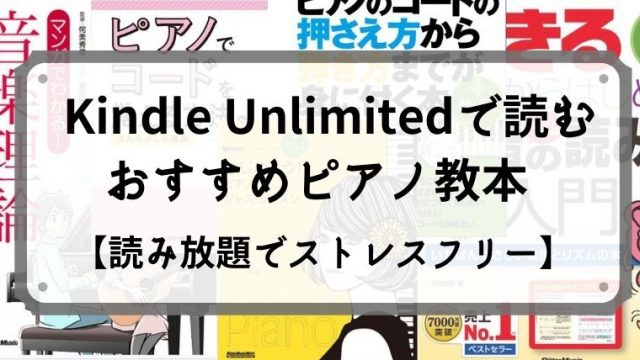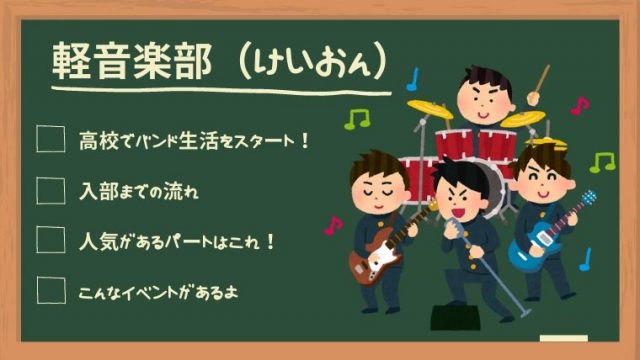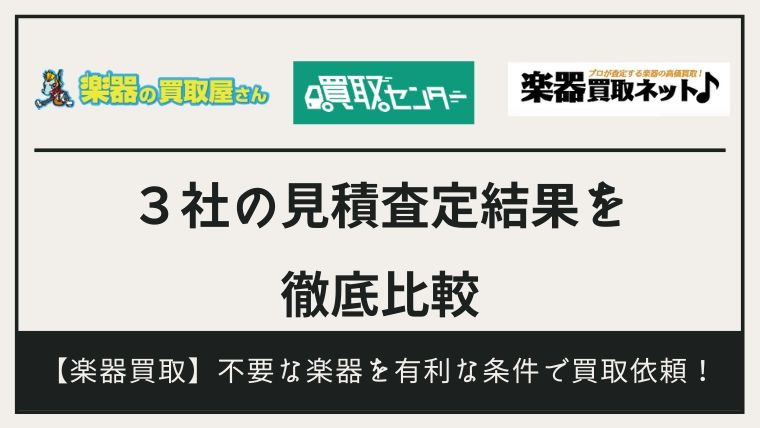音楽の世界でマルチプレイヤーという言葉があります。
簡単にいうと「一人で複数の楽器を演奏できる人」という意味になりますが、音楽好きの中でもプレイヤー志向の方からすると、とてもうらやましい存在ではないでしょうか。
なぜかというと、それぞれのパートの立場で演奏を楽しむことができるからです。
今回はそんなマルチプレイヤーの様々なことについて、自分自身の経験も交えて整理、考察してみたいと思います。
- マルチプレイヤーの定義
- マルチプレイヤーの利点
- マルチプレイヤーの具体例
- メイン楽器とサブ楽器のおすすめ組み合わせ
- マルチ度を判定しよう!
それではいってみましょう!
マルチプレイヤーの定義
まずはマルチプレイヤーの定義を明確にしましょう。以下wikipediaの記載内容です。
基本的には、(ボーカルを除く)複数の楽器の演奏が出来るプレイヤーを指す。ただし通常は、以下の条件が必要とされる。
各楽器が、基本構造の異なる物であること例えば「ギターとキーボード」、或いは「ギターとドラムス」。これに対して「ギターとベース」、或いは「ピアノとキーボード」は、基本構造にあまり相違が無いため、2者を演奏出来てもマルチプレイヤーと呼称される例はあまり無い(ただし複数の種類のキーボードを駆使する演奏技法を「マルチ・キーボード」と呼称する場合がある)。
各楽器ごとに、一定以上のレベルの演奏能力を獲得していること。片方の楽器が卓越した演奏レベルを有しているのに対して、もう片方の楽器がコードを幾つか鳴らす事が出来る、という程度の能力である場合は、マルチプレイヤーと呼称される例はあまり無い。
引用:wikipedia マルチプレイヤー(音楽)
ほぼこの記載内容がマルチプレイヤーの概要を言い表していると思います。
気になるのは、本文下部の「もう片方の楽器がコードを幾つか鳴らす事が出来る、という程度の能力~」という部分です。
つまり…
このような場合は、マルチプレイヤーとは見なされない…ということですね。
正直、ギターで3コード(例えば、C,F,Gなど)を覚えるのは、その気になれば1日で出来ます。
そのような基準でいくとマルチプレイヤーだらけになってしまいます。そうではなくて、各楽器の特性を理解し、様々な表現を行うためのテクニック等が備わっている必要があります。
それだけの努力が必要だからこそ、マルチプレイヤーはある意味一目置かれる存在であると思います。
マルチプレイヤーの利点

ではマルチプレイヤーであるとどのような利点があるかについて整理してみます。
個人的には以下の項目を上げさせていただきます。
- とにかく楽しい!
- 急な代役など臨機応変な対応ができる
- 各楽器の特性を理解していることでバンドアンサンブルが深まる
①とにかく楽しい
凄く単純な理由です。とにかく楽しい。
バンドの各パートは、それぞれ別の風景を見ています。
ドラマーは割と全体を俯瞰してみていますし、ギターは自分がおいしいとこを考えています。キーボードは他のパートを補完するように動いています。
まぁ上記は一例で人によっても違いますが、それぞれ立場によって考えていることが違うのは確かです。
各パートの特徴は以下の記事にまとめていますので、こちらも参考にどうぞ。

マルチプレイヤーであれば、そういった立場を変えてバンドを楽しむことが出来るのです。
②急な代役など臨機応変な対応ができる
これは固定のバンドというよりは、セッションや遊びで集まる際などで、足りないパートがあった時にサッとそのパートに入って、演奏を成立させられちゃうよ…というメリットです。
私は職場で軽音部を結成しており、練習日にメンバーが残業…なんてこともあります。
そんなとき例えばドラムがいないと練習自体成り立たなくなりますので、鍵盤からドラムに変わったりします。(ギターがいれば鍵盤はなくても大丈夫だったりします。)
そういった意味で実用性もあります。
③各楽器の特性を理解していることでバンドアンサンブルが深まる
利点という観点からみればこちらが一番の理由です。(基本は①と同じですが、ちがった角度から見たものです。)
これを説明するために、別ジャンルの事例で説明します。
日本には平安時代から現在まで形を変えることなく続く「雅楽」というものがあります。
この雅楽の第一人者として東儀秀樹さんが有名ですが、その東儀秀樹さんが自身のWEBサイトで次のように語っています。
「管絃」は楽器だけの演奏表現で、正式には笙(しょう)、篳篥(ひちりき)、龍笛(りゅうてき)の三種の管楽器、琵琶、箏の二種の絃楽器、太鼓、鞨鼓(かっこ)、鉦鼓(しょうこ)の三種の打楽器の編成で演奏されます。指揮者のいないこの演奏はアンサンブルの極致ともいわれるもので、その神髄に迫る演奏をするには担当する楽器に精通することはもちろんですが、共に演奏される八種類の楽器の動きを充分に把握し、演奏者同士の息(意気)や、間を感じ合うことが大切になります。そのため雅楽師というのは主の管楽器のほか、絃楽器のひとつ、打楽器すべて、そのほか舞や歌もマスターしなければ成り立たないのです。
引用:東儀秀樹offical Websaite 「雅楽とは」
雅楽は三種類の管楽器、二種類の弦楽器、三種類の打楽器で構成されるもので、雅楽の演奏者はメインで担当する楽器以外にも、八種類の楽器全てに対してマスターすることが求められているのです。
これは雅楽に指揮者という存在が居らず、アンサンブルを高めるためにそれぞれの動きを十分に把握、つまり自分がそれぞれの立場を知っていれば話は早いわけですね。
指揮者がいないといえば、ロックだってポップスだって、バンドはほぼそうですよね!
各楽器のタイミングの取り方や音色設定の特徴、楽器演奏上の悩み…色々な面でその立場を分かるからこそ、優しくなれるし、厳しくもなれる。
マルチプレイは自分のためでもあり、仲間のためでもあるといえます。
ただし、自分の本来パートをおざなりにして、他パートに中途半端にかまけていると不評を買いますので、注意しましょう。
マルチプレイヤーの具体例

ここでは実際にマルチプレイヤーとして活躍されているアーティストを紹介します。
奥田民生
UNICORNで主にメインボーカルとギターを担当している奥田さんですが、ドラマーとしての腕前も相当なものです。
またシングル曲の全楽器を一人で演奏するということも割と早く始めており、マルチプレイヤー歴は長い。1992年に発売された奥田民生のソロシングル「休日/健康」は全パートの演奏を一人で行っています。
また最近ではスキマスイッチの全力少年をプロデュースしており、そこでもギター、ベース、ドラム、パーカッションを担当しており、奥田民生ワールドを展開しています。
ちなみにUNICORNでは盟友、ABEDONもマルチプレイヤーとして有名です。
布袋寅泰
日本を代表するギタリストの一人布袋さんですが、ギターの印象が強すぎてピアノの腕前も確かなことはあまり知られていないかもしれません。
ピアノは幼少期の習い事をして始めており、中学生でギターを志すまで続けられていたようです。
またピアノだけでなく、ベースはもちろんドラムも叩けるため自身の演奏でレコーディングも行っています。
動画は今井美樹へ作曲した「PRIDE」をピアノの弾き語りでセルフカバーしたもの。
イヤー名曲ですね。しっとりしたピアノもいい感じ。
大橋トリオ
バリバリのマルチプレイヤーといえば大橋トリオの名前が真っ先にあがるでしょう。
大橋トリオはギターやドラムの腕前も相当なものですが、特にピアノは大学のジャズピアノ科で学んでいたこともあり本格的です。
また、マルチプレイヤーとしての意識も相当高いようで、音楽ナタリ―でのインタビューでで次のように語っています。
コンサートで言うと、2008年の1月に東京国際フォーラムのホールCで見たルーファス・ウェインライトがすごかったですね。 ―中略― 全員いろんな楽器ができるんですよ。さっきまでギターを弾いていた人がピアノを弾き始めたらめちゃくちゃうまかったり、ホーン隊がみんなでコーラスするんですけど、それもすごくうまくて。日本のアーティストでそこまでできる人って、いないんですよね。僕はいろんな楽器をやるようにしていて、マルチプレイヤーって言っていますけど、サポートメンバーにもそうあってほしいんです。ルーファスのバンドメンバーを見ちゃっているから、「目指すならそこでしょ」と。今集めているメンバーは、やれることの幅がなるべく広い人で固めるようにしています。
引用:音楽ナタリ―
つまり自分だけではなくて、サポートメンバーにもそのような人を集めていると。なかなかの高レベルです。
マルチプレイヤーを目指そう!
上述の「マルチプレイヤーの利点」であげたように、色んな楽器を扱えるということは音楽活動する上でとても有利です。是非目指してみることをお勧めします。
その際、メイン楽器に対するサブ楽器という位置づけで、どのような組み合わせがいいか、個人的なおすすめを併せてご紹介します。
メイン楽器:ギター
メイン楽器がギターの方にはキーボードをおすすめします。
【理由】
ギターもキーボードもコードを弾ける楽器ですが、ギタリストの場合はコードの仕組みを理解して弾いているというよりは、フォームで覚えていることが多いです。
ギターの場合は、同じフォームのまま横にずらせば別のコードを弾けちゃうという楽器の特性上の理由もあるでしょう。
キーボードの場合は、音程が横に並んでいるためコードの構成音等を理論的に把握しやすいため、その知識をギターにも還元できるのです。
またギターとキーボードはバンドアンサンブルの中で同じ役割を担うことが多いので、通常は音程上の棲み分け等を考慮する必要がありますが、同じ立場を経験することでその辺のコミュニケーションがとりやすくなります。
メイン楽器:キーボード
メイン楽器がキーボードの方にはドラムをおすすめします。
【理由】
キーボードもリズム楽器の一つではありますが、バンドアンサンブルの中ではリズムへの意識が薄くなりがちな面があります。
そのあたりの要因の一つとして音色があります。
キーボードにはピアノやオルガンのように音の立ち上がりの速いものもありますが、ストリングスやパット系音色では全体を包み込むような雰囲気を出すだめ、音の立ち上がりが緩やかなものも多いです。
そのような役割をこなしていると細かいリズムへの意識が薄れてくるのです。
ドラムを経験するとリズムを意識せざるを得ません。しかも、各小節内の音符の位置を正確に理解する必要があります。
そういったバンドアンサンブルの意識面醸成の面でも効果的と考えます。
マルチ度を判定しよう
 こちらが現在の私の部屋です。いろんな楽器の練習ができるようにしています
こちらが現在の私の部屋です。いろんな楽器の練習ができるようにしていますマルチ度を判定しようーということで。私カフェラン自身も一応複数楽器の経験があるため、こんなケースですが「マルチ、いけてますか?」というのを確認する意味も含めてさらしてみます。
各楽器の現状は以下のとおりです。
キーボード
一応バンドではメインの担当楽器とさせていただいています。
弾くのが好きなのはジャズ、やっているバンドはハードロック…ということでジャンルは幅があります。
バンドではオルガンやシンセリードなどを弾くことが多く、その反面自宅ではピアノばかり弾いています。
クラシックは通っていないので、少し難しいクラシックとなるとかなり練習しないとモノになりませんし、五線譜の初見演奏は苦手です。コード譜での初見演奏であれば対応可です。
ギター
ギターは20代前半に始め、その後ちょこちょこと続けております。
バンドでギターを担当していた時代があり、割とシンプルなロックばかりやっていました。
よってテンションを含む凝ったコードはあまり押さえ慣れていません。
ただし、一般的なJPOP等のギターアレンジであればおそらく対応可能です。
ベース
こちらも30歳くらいのときに、バンドでベースを担当していたことがあります。
このときはLOUDNESSのコピーバンドだったので、かなりテンポが速めの曲ばかりやっていた印象があります。
ギターの延長でのベース、そしてハードロックというジャンルということもあり、ピック弾きです。指弾きは苦手です。
自分でオリジナル曲でベースラインを作れるレベルかというと、まだ経験が必要だと感じています。
ドラム
ドラムはここ1年くらいで始めた楽器です。
職場の軽音部で演奏する機会があるぐらいで、ゆる~い経験です。
基本となる8ビートと数種類のフィルインのバリエーションがある程度の段階です。
おそらく、wikipediaに掲載されていた「いくつかのコードを弾けるぐらいじゃダメ」というのに相当するレベル感だと思います。まだまだこれからですね。
まとめ
マルチミュージシャンの定義と利点を中心に説明させていただきました。
私自身の経験楽器では、キーボードとギターはそれなりに経験年数があるので対応可能ですが、ベースとドラムはもっとやっていきたいと感じています。
比較基準にならないレベルかと思われますが、一応基準としてマルチ度判定に使っていただければと思います。
あくまで自身のメインパートを磨いていくことが本道だと思いますが、ちょっと余裕のある方は他パートで寄り道はいかがですか?
道草かもしれませんが、とってもいい出会いがあるかもしれませんよ。
Amazonが提供する”Amazon Music Unlimited”は、
6500万曲が聴ける音楽サブスクリプションの中でもトップクラス!
今なら30日無料で聴き放題です。是非この機会に!